「金融教育は早いうちから」とよく聞くけれど、実際に子どもに話してみると…「うん、わかったー」と言いながら、3分後には完全に聞いていない。はい、これがわが家の現実です。やっぱりまだ早いのかな?と感じつつも、「でも伝えたい!」という気持ちの間で揺れ動いています。
お小遣いをあげてみたけれど…
実は一時期、お小遣いをあげていました。でもすぐに壁にぶつかります。
理由はシンプル。おじいちゃん・おばあちゃんが、子どもに欲しいものを結構なんでも買ってくれるんです。さらにスーパーに行くと「今日はお菓子買っていいよね?」とほぼ自動的におやつゲット。結果として、「お小遣いって何の意味があるんだろう?」という状態に。
上の子と下の子で金額を分けるべきか?一緒でいいのか?──そんな疑問もあって、一度お小遣い制度はストップしました。でもこれ、親あるあるじゃないですか?「みんなのおうちはどうしてるんだろう?」と本気で聞きたいです。
「本当に欲しい?」を考える練習
一方で、わが家なりの工夫もあります。それは「欲しいものは買ってもいいけど、本当に欲しいかどうか一度考えてみよう」ということ。
たとえば、おもちゃ売り場で「これ欲しい!」と言われたとき。すぐに買うのではなく、「他にもいろいろ見て、一番欲しいものを探したら?」と提案します。ただ…子どもってやっぱり目の前にあるものに弱い。最終的には「やっぱりさっきの!」となることが多いんですよね。まあ、それもまた経験でしょう。
親としての願い
将来、子どもたちには「お金を気にせず生活できる大人」になってほしいと思っています。でも現実は、そんなに稼げるのは一握りの人。だからこそ、まずは貯蓄率を大事にする感覚を身につけてほしい。
無駄を減らしつつ、満足度はちゃんとキープできる──そんなお金との付き合い方が理想です。もちろん「節約!節約!」と縛りすぎて、人生の楽しみを削るのはNG。お金はあくまで人生を豊かにする道具ですからね。
まとめ:正解はないから、試行錯誤
結局のところ、「子どもへのお金教育」に正解はありません。
わが家も「話してみる→聞いてない」「お小遣いあげてみる→意味が薄れる」の繰り返しです。でも、こうした試行錯誤自体が、きっと将来の子どもに伝わると信じています。
これを読んでくださったみなさんの家ではどうしていますか?
お小遣い制度のルールや工夫があれば、ぜひ教えてください。わが家もまだまだ迷走中なので、一緒に模索していけたらうれしいです。
📩 ブログ読者限定のお得情報や、月1回の資産推移報告も発信中!
X(旧Twitter)やブログをフォローして、いっしょに資産形成していきましょう。
👉 ブログトップページへ戻る
👉 X(旧Twitter)もフォローする
最後に一言。投資は自己責任が基本です。このブログは私の思考のアウトプット。皆さんもよく考えて、楽しく賢く資産運用してください!

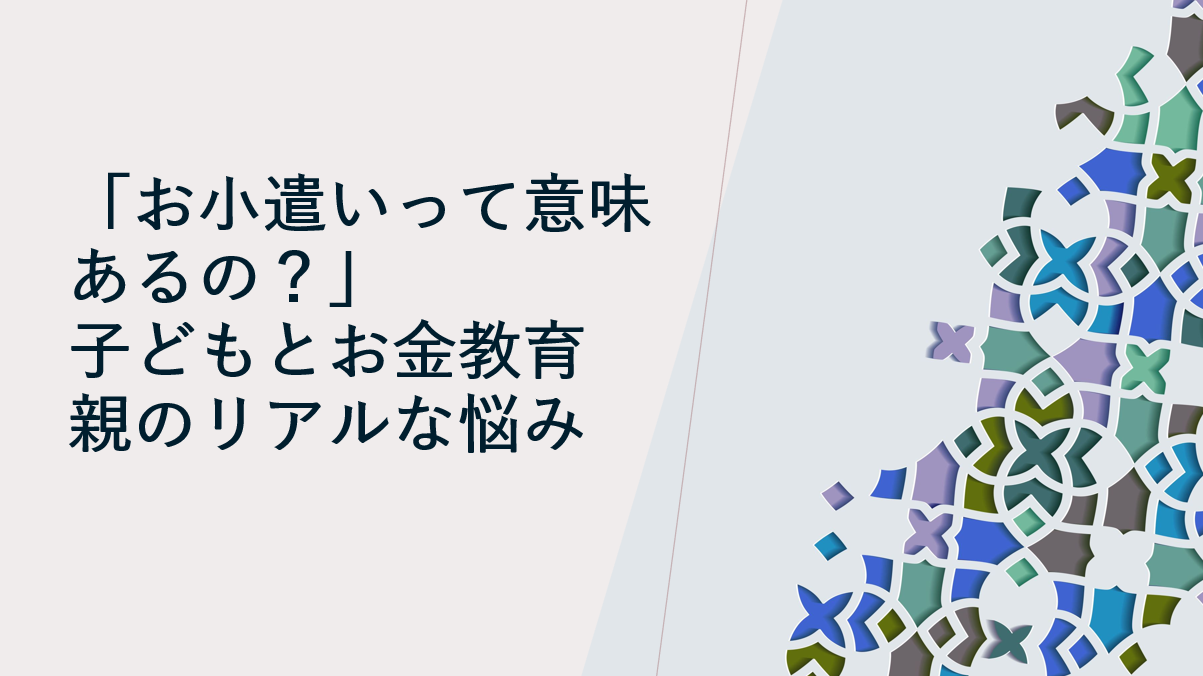
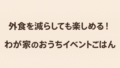
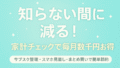
コメント